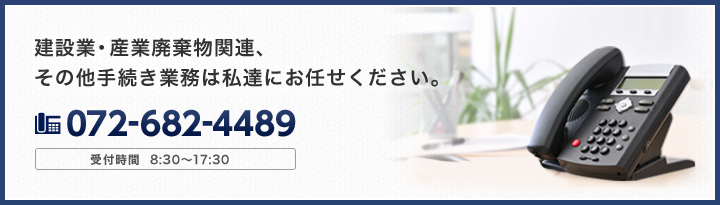第2種電気工事士技能試験対策講習会第1回目を開催しました。
大阪府高槻市で建設業許可申請及び産業廃棄物処理業申請を中心に営んでおります行政書士浜田温平事務所の浜田です。 前職で、電気工事士の職業訓練指導員を6年程度、勤めていた関係で毎年、「電気工事士試験対策講座」弊所で開催させていただいております。昨日は技能試験対策の第1回目ということで、単線結線図を複線図に書き直すことを練習しました。試験時間は40分ですが相当手際よく作業を進めていかないと合格できません。因みに、電気工事業の専任技術者要件としては、第1種電気工事士免許を取得しているかまたは、第2…